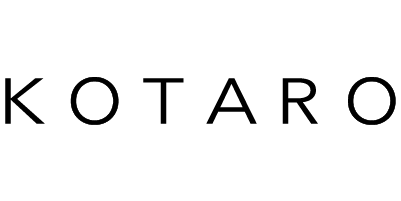長襦袢の寸法を決めるとき一番大切なことは、理想の衿合わせができるかどうか。
長襦袢を着用した時、衿合わせができることと、理想の衿合わせができることは全く別の事です。KOTAROでは、理想の衿合わせができる長襦袢寸法にすることを第一優先しています。

長襦袢の着用可・不可の判断基準
長襦袢の着用可能かどうかの判断は、衿合わせができるかどうかが判断基準。
どんな角度でも衿合わせができれば、着用可。衿合わせができなければ着用不可と判断します。
衿合わせ以外に身丈や裄の問題もありますが、身丈が多少短くても長くても着用はできるし、裄も多少違っていても袖が見えるだけで着用はできます。衿合わせができない時だけが、何をどうしても着用できない時です。
長襦袢の寸法が自分に合っているかどうかの判断基準
長襦袢を着用したとき、理想の衿合わせができるかどうかが、自分に合った寸法かどうかの判断基準です
理想の衿合わせにし、胸紐を締め、伊達締めをし、身体を動かしてみます。部屋の中を歩いたり、座ったり、トイレへ行ってみたりします。そうやって動いた後、衿の着崩れがなければ寸法が合っていると判断。衿が動くのではれば寸法が合っていないと判断します。
胸紐を締めた時点で窮屈感があったり、衿が浮いたり、身八つ口が浮いている時は、その時点で合っていないと判断します。
腰紐の代わりにコーリンベルトを使ったり、伊達締めも絹物ではなく滑りにくい物を使用すると衿の動きが変わるので、古典的な胸紐と伊達締めで試してみることをおすすめします。
長襦袢は衿のための寸法にする
極端なことを言えば、長襦袢は衿のためにある、と思っています。
衿合わせが上手く行く寸法にすると、下半身の布がダブついたりしますが、後身頃から前身頃まで繋がっているため全ての理想を叶えることはできません。見えない部分の着心地も軽視はできませんが、やはり一番は長襦袢の衿合わせがキチンとできていることだと思っています。
まとめ
着物の寸法から長襦袢の寸法を割り出すと、着用可能な長襦袢は出来上がるけど、理想の衿合わせができる長襦袢は出来上がらないと思っています。理想の衿合わせができる長襦袢を誂えたいと思ったら、もう一歩踏み込んだコミュニケーションが必要です。
自分で寸法を探る場合は、自分サイズだと言われている物よりも、2サイズ大きいものを着てみたり、2サイズ小さい物を着てみたりします。そうすると、大きめの方が着心地が良い・小さめの方が着心地が良い、など、今ある寸法をどう変化させればよいかが分かります。
長襦袢の着心地が良いと、着物の着心地も格段に良くなります。
ぜひ着物と同じくらい長襦袢の寸法にも注目してもらえると嬉しいです。
関連記事
-
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
衿の着心地を良くしたいなら、肩明き・繰越・付込みを見直すこと。
着物と長襦袢の衿の添いを良くしたいなら「肩明き」「繰越」「付込み」の寸法を揃えることです。この3つさえ同じ寸法になっていれば、衿の添いは抜群です。 肩明き・繰越・付込みの場所 下の写真、後ろから見た図の衿付近に「肩明き」 […] -
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
長襦袢の寸法で一番大切なことは、理想の衿合わせができるかどうか。
長襦袢の寸法を決めるとき一番大切なことは、理想の衿合わせができるかどうか。長襦袢を着用した時、衿合わせができることと、理想の衿合わせができることは全く別の事です。KOTAROでは、理想の衿合わせができる長襦袢寸法にするこ […] -
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
声を大にして言いたい。 長襦袢 こそ自分の着方にあった寸法で誂えたほうが良い。
着物を、綺麗に着たい・着心地良く着たい・着崩れをなくしたい、と思ったら、絶対に必要なのは着心地の良い 長襦袢 です。長襦袢の着心地が良いだけで、衿合わせも衣紋の抜き具合もバチッと決まります。ここでは、長襦袢こそ自分寸法で […] -
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
胸を包むように衿合わせがしたいと思ったら。- 長襦袢 の寸法について-
胸を包むように衿合わせがしたいと思ったら、胸を包むだけの巾の広い長襦袢を作らなければいけません。単純に着物の寸法から割り出す 長襦袢 の寸法は本当に胸を包むだけの巾のある長襦袢なのでしょうか。今回は、手持ちの長襦袢が胸を […] -
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
長襦袢9枚×3パターンの着用を写真に収めました。
昨年(2023年)は「長襦袢」をテーマに色々な寸法で9枚の長襦袢を仕立てました。この9枚の着用画像を、①衣紋を抜かずに着用した場合、②衣紋を適度に縫いて着用した場合、③衣紋をたくさん縫いて着用した場合、の各長襦袢3パター […] -
 長襦袢の寸法
長襦袢の寸法
長襦袢の袖付 が着物の袖付より短すぎると問題は起こるのか?
長襦袢の袖付 寸法は、必ず着物の袖付寸法よりも短く仕立てます。標準寸法は、着物の袖付寸法−2分程度です。この寸法は着物よりも短ければどんな寸法でも問題ないのでしょうか?今回は、標準寸法よりもさらに短い、①着物の袖付寸法− […]
講座では『どんな形の長襦袢を作るのか』を決めるとことから一緒に考えていきます。
次回2026年3月13日、東京にて講座を開催します。